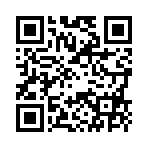子供たちはなぜ野菜嫌いが多いかを再検証する。
2015年04月17日
只今水を飲みながら体の疲れを嘆きつつ文章の手直しをしている。以前子供たちの魚嫌いについて書いたことがある。今回は子供たちの野菜嫌いについて考えてみた。魚嫌いよりも野菜嫌いは深刻な感じがする。

そもそも人類というかアウストラロピテクスやネアンデルタールの時代にこの人類の祖先は野菜というか当時の野草のようなものは食していたのであろうか?これは非常に大きな疑問である。本来であれば人類の祖先はマンモスの肉などを食べていたわけで肉食だったと思われる。となると古代からのDNAを考えれば野草を食べるというのは入っていない感じがする。
それがあるときに植物を栄養として取り込むということに対して人類の祖先たちが気づき米を主食にするようになり、野菜を食べ始めたというのが起源である。しかし古代の野草は今のような美味な野菜というものがなかったわけで…そのDNAは現代に受け継がれ野菜嫌いを誘発しているものだと思われる。
嫌いな野菜の代表格として思い浮かぶのがまず「ピーマン」である。ピーマンはもともと唐辛子の変種で、外側の果肉を食べるというものである。栄養素としてビタミンCの含有率が高くてレモンと比べて手軽に取れる物とされている。しかし火の通し方が悪いと独特の苦味を発することから子供たちには敬遠されている。主な用途としてはチンジャオロースーや野菜炒めといった炒め物に用いられることが多く、またピーマンにハンバーグの種を詰めた肉詰めであったりピザトーストのトッピングに青みとして乗せたりもする上に天ぷらなんかにも使える。火を通せば独特の甘味が出てうまいのだが、子供のうちはやや食べづらい感じがする。実際のところ学校給食ではピーマンを使用しないメニューが多くあるというのが現実のようだ。
西の横綱は「ニンジン」である。ニンジンはピーマンと違う根菜類で煮物からサラダまで用途が幅広い。においなどもきつくなくベータカロテンを含む栄養素からして成長には欠かせないものなのだが、煮込むとどうもズクズクした食感になることやもう一つ中途半端で釈然としない甘味があることなどがどうしても敬遠されがちである。また生でサラダ等に入れたときなど今度は硬くて食べにくいなどの理由も重なりどうも敬遠され気味である。学校給食ではピーマンとは逆で毎日のようにニンジンが入っている。
 その下にくるのが「シイタケ」である。シイタケの場合キノコというのもあって独特の香りがするためどうしてもそこを敬遠するほか、生シイタケを炒め物などに入れると舌触りが気持ち悪いという理由があるようでこれも敬遠されている。
その下にくるのが「シイタケ」である。シイタケの場合キノコというのもあって独特の香りがするためどうしてもそこを敬遠するほか、生シイタケを炒め物などに入れると舌触りが気持ち悪いという理由があるようでこれも敬遠されている。
筆者は生のトマトがダメである。甘いというか何というかどっちつかずな味と種の食感は寒気がしてしまうほどで幼い頃からダメであった。
という感じで大人になってまで野菜嫌いというのは続いている。克服法は食べる側以上に料理する方が握っている。いわゆる火の通し方だったり食感を消したりなどの細やかな工夫がどうやら必要のようである。いろいろ知恵を絞って野菜嫌いを克服しよう。

そもそも人類というかアウストラロピテクスやネアンデルタールの時代にこの人類の祖先は野菜というか当時の野草のようなものは食していたのであろうか?これは非常に大きな疑問である。本来であれば人類の祖先はマンモスの肉などを食べていたわけで肉食だったと思われる。となると古代からのDNAを考えれば野草を食べるというのは入っていない感じがする。
それがあるときに植物を栄養として取り込むということに対して人類の祖先たちが気づき米を主食にするようになり、野菜を食べ始めたというのが起源である。しかし古代の野草は今のような美味な野菜というものがなかったわけで…そのDNAは現代に受け継がれ野菜嫌いを誘発しているものだと思われる。
嫌いな野菜の代表格として思い浮かぶのがまず「ピーマン」である。ピーマンはもともと唐辛子の変種で、外側の果肉を食べるというものである。栄養素としてビタミンCの含有率が高くてレモンと比べて手軽に取れる物とされている。しかし火の通し方が悪いと独特の苦味を発することから子供たちには敬遠されている。主な用途としてはチンジャオロースーや野菜炒めといった炒め物に用いられることが多く、またピーマンにハンバーグの種を詰めた肉詰めであったりピザトーストのトッピングに青みとして乗せたりもする上に天ぷらなんかにも使える。火を通せば独特の甘味が出てうまいのだが、子供のうちはやや食べづらい感じがする。実際のところ学校給食ではピーマンを使用しないメニューが多くあるというのが現実のようだ。
西の横綱は「ニンジン」である。ニンジンはピーマンと違う根菜類で煮物からサラダまで用途が幅広い。においなどもきつくなくベータカロテンを含む栄養素からして成長には欠かせないものなのだが、煮込むとどうもズクズクした食感になることやもう一つ中途半端で釈然としない甘味があることなどがどうしても敬遠されがちである。また生でサラダ等に入れたときなど今度は硬くて食べにくいなどの理由も重なりどうも敬遠され気味である。学校給食ではピーマンとは逆で毎日のようにニンジンが入っている。
 その下にくるのが「シイタケ」である。シイタケの場合キノコというのもあって独特の香りがするためどうしてもそこを敬遠するほか、生シイタケを炒め物などに入れると舌触りが気持ち悪いという理由があるようでこれも敬遠されている。
その下にくるのが「シイタケ」である。シイタケの場合キノコというのもあって独特の香りがするためどうしてもそこを敬遠するほか、生シイタケを炒め物などに入れると舌触りが気持ち悪いという理由があるようでこれも敬遠されている。筆者は生のトマトがダメである。甘いというか何というかどっちつかずな味と種の食感は寒気がしてしまうほどで幼い頃からダメであった。
という感じで大人になってまで野菜嫌いというのは続いている。克服法は食べる側以上に料理する方が握っている。いわゆる火の通し方だったり食感を消したりなどの細やかな工夫がどうやら必要のようである。いろいろ知恵を絞って野菜嫌いを克服しよう。
タグ :さんさん広場 さんさん 祗園 祇園町野菜嫌い 古代人のDNAピーマン 火の通し方 学校給食 ニンジンシイタケ ベータカロテン 成長期貸会議室 貸会議 イベント セミナー室 貸 安 激 博多 駅 西鉄 バス
恵方巻
神経痛
☆ブログ連載始めました☆【メンバー美波の”連載”】「グルグル思考を止める方法について」 ※英訳有
【お薬って、太りませんか?】
【小学校2年で教わったワンランク上の遊び】
私の大切にしているもの ”10がつく日” 】
神経痛
☆ブログ連載始めました☆【メンバー美波の”連載”】「グルグル思考を止める方法について」 ※英訳有
【お薬って、太りませんか?】
【小学校2年で教わったワンランク上の遊び】
私の大切にしているもの ”10がつく日” 】